ペン字を習い、少しずつ字が綺麗になってくると嬉しいですよね!
せっかく上手に書けるようになったら、資格を取ってみるのもいいかもしれません。
その際、
「ペン字の資格ってどんなものがあるのかな?」
「受験にいくらくらいかかるんだろう?」
こんな疑問は浮かんでこないでしょうか?
実は硬筆やペン字についての資格はいくつもあり、特徴も異なります。更に万年筆が使えるかどうかも資格によってバラバラです。
この記事では、硬筆・ペン字についての資格の情報を初心者にも分かりやすく丁寧にまとめました。
この記事を読むことで、自分に最適の硬筆・ペン字の資格を選ぶことができるようになります。
 ちゃくま
ちゃくま5つのペン字の資格について
①資格の概要
②万年筆が使えるか
③その資格がオススメの人
をそれぞれ紹介していくよ!
[日本書写技能検定協会]硬筆書写技能検定


硬筆書写技能検定とは、文部科学省後援の検定試験
1964年にペン字検定の名称でスタートしました。1990年に現在の名称に変更され、現在までに硬筆だけでも延べ1,000万人が受験しています。
毛筆と硬筆があり、いずれかを受験することができます。
| 主催団体 | 一般財団法人 日本書写技能検定協会 |
| 級位 | 6級・5級・4級・3級・準2級・2級・準1級・1級 |
| 取得方法 | 実技・理論に関して各級ごとに設定された合格点以上の成績をおさめること |
| 試験日程 | 年3回 |
| 試験会場 | 全国各地の試験会場で一斉に実施 |
| 受験資格 | 年齢・学歴などの制限はなく誰でも受験可 1回の試験で複数の級位を併願することはできない 事前の申込が必要(試験日の約1ヵ月前まで) |
| 試験内容 (3級) | 試験時間:70分 審査基準:硬筆書写一般の技術、および知識をもって書くことができる 受験費用:3,000円 合格率(令和3年累計):71.0% |
万年筆は級位・設問によっては使用できる
硬筆書写技能検定の試験は級位によって内容・使用できる筆記具が異なります。具体的には以下です。
6級~4級 … 全設問で万年筆は使用不可
3級~1級 … 一部の設問で万年筆は使用可(万年筆が使用できない設問もある)
万年筆1本だけで受験できる、、という試験ではありません。
硬筆書写技能検定は、履歴書に書きたい人にオススメ!
他のペン字の通信教育などの級位と違い、文部科学省後援の検定試験ですから公的性があります。
資格として『○年第○回文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定○級合格』と履歴書に書くことができます。
また、特定の大学、短大、高校、各種・専修学校で、入試の際の合否判定で優遇、または一定の点数が加算、増加単位として認定する学校が増加しています。



例えばユーキャンのボールペン字講座は、硬筆書写技能検定にピッタリ!3級合格に向けたガイドブックもついてるよ。


[公益財団法人日本書道教育学会] 全国ペン硬筆検定試験


全国ペン硬筆検定試験は、書道界全般に通用する普遍的な段級
日本書道教育学会は1950年に設立され、現在は全国で10万人が本会の書道教育機関で学んでいます。
| 主催団体 | 公益財団法人日本書道教育学会 |
| 級位 | 級位、助教、司教、師範 (級位は成績により上級・中級・初級のいずれかに認定) |
| 取得方法 | 実技と理論 |
| 試験日程 | 年2回、5月と10月 |
| 試験会場 | 指定された期間中に郵送にて提出(ただし師範は会場受験) |
| 受験資格 | 師範・司教・助教:18歳以上 級位:制限はなく誰でも受験可 |
| 試験内容 (ペン硬筆・級位) | 審査基準: ・楷書、行書、ひらがなを正しく書く技能をもち、字形を整えて美しく書くことができる。 ・漢字かな交じり文を体裁よく書くことができる。 硬筆に関する用具・用材・用語について正しく広い知識と表現力をもっている。 ・楷書、行書、かなの古典を正しく臨書することができる。 ・初歩的な創作ができる。 ・常用漢字表、常用漢字字体表、常用漢字音訓表についての知識をもっている。 受験費用:3,500円 |
万年筆は、使用可能!
使用可能な筆記具は試験によって決められますが、基本的に万年筆を使って問題ありません。
一方で、万年筆以外の指定がある可能性もゼロではないので、必要に応じて適切な筆記用具を使いましょう。
全国ペン硬筆検定試験は、これをきっかけに筆の道を始めたい人にオススメ!
全国ペン硬筆検定試験は、歴史と伝統に裏付けられた検定試験として全国的に実施されています。
検定試験をきっかけに本格的に実力を付けたい人は、日本書道教育学会に入会すると添削が受けられたり、全国ペン硬筆検定試験とは別の段級認定にチャレンジすることもできます。
日本書道教育学会では硬筆の他に、毛筆、篆刻、写経などの通信講座もあります。



篆刻はなかなか他では習えないので面白そうだね!
[日本ペン習字研究会]日ペンの師範認定試験


日ペンの師範認定試験は、五段までは無料で審査を受けられてお得
昭和7年設立と歴史がありペン字教育界をリードしてきました。指導実績は100万人以上です。
| 主催団体 | 日本ペン習字研究会 |
| 級位 | 10級~五段、推薦、準師範、師範 |
| 取得方法 | 五段までは月例競書、その後は昇格試験 |
| 試験日程 | 五段までは毎月、推薦・準師範試験は3月と9月、師範試験は9月 |
| 試験会場 | 指定された期限までに課題を郵送 |
| 受験資格 | 制限はなく誰でも受験可 |
| 試験内容(規定部) | 「ペンの光」に記載のお手本に従って課題を書く 受験費用:五段までは無料(ただし「ペンの光」購読料と、課題用紙代は必要) |
万年筆は、使用可能!
日ペンの師範認定試験のうち級位取得ができる「規定部」の課題については、下記の説明があります
筆記具は、ボールペン、万年筆(デスクタイプ含)、つけペンのいずれかを使用してください
級位に関わらず、お気に入りの万年筆を使ってOKです!
日ペンの師範認定試験は、本格的な学習でしっかり上達したい人にオススメ!
ペン習字の競書誌「ペンの光」には、課題別のお手本、上手に書くコツの解説、提出者全員の級・段、提出作品への批評、優秀な作品が掲載されています。
課題を提出すると段級位認定され、その後、昇級、昇段していくので上達の過程がより明確になります。
[ユーキャン]日本書道協会 技能認定制度


日本書道協会は、ユーキャン傘下の団体
日本書道協会は、(株)ユーキャンの傘下の団体です。1973年に設立し、現代書道講座や現代ペン字講座の開講と書道やペン字の学習を長年行っています。
その日本書道協会が、受験者の書の実力を認定するものが「技能認定制度」です。
| 主催団体 | 日本書道協会 |
| 級位 | 5級~九段(実用ボールペン字部門) |
| 取得方法 | 課題の提出 |
| 試験日程 | 特になし ・最初の課題:5級課題をホームページからダウンロード、いつでも提出可能 ・2回目以降の課題:前回の審査結果(合格・不合格ともに)の通知と共に新しい課題が発送され、いつでも提出可能 |
| 試験会場 | 指定された期限までに課題を郵送 |
| 受験資格 | 制限はなく誰でも受験可 |
| 試験内容 (実用ボールペン字部門) | ホームページからダウンロードできる課題に取りくみ提出 受験費用:無料(最初の級の免許料として税込で3,000円のみ支払い必要) |
万年筆は、使用できない
日本書道協会の技能認定制度では、使用する筆記用具について下の説明があります。
「筆記用具には黒インクボールペンを使ってください」
残念ながら、万年筆を使った受験はできません
日本書道協会の技能認定制度は、自分のペースで受験したい人にオススメ!
級位を取得するためには所定の課題を提出する必要がありますが、特に締め切りはありません。そのため自分のペースで級位取得を進めることができます。
仕事の忙しさが不規則だったり、まとまった時間をいつとれるか分からない人には嬉しいですね。
[パイロット]パイロットペン習字 検定試験


パイロットペン習字の検定試験は、硬筆書写技能検定に準拠
| 主催団体 | パイロット |
| 級位 | 10級~七段 |
| 取得方法 | 課題の提出 |
| 試験日程 | 年12回(毎月末が提出期限) |
| 試験会場 | 指定された期限までに課題を郵送 |
| 受験資格 | パイロットのペン習字通信講座を受講している必要あり |
| 試験内容 (実用ボールペン字部門) | ホームページに記載されている課題(お手本なし)に取りくみ提出 受験費用:パイロットのペン習字通信講座の代金(新規:17,600円、継続:12,000円)に含まれている |
万年筆は、使用可能!
パイロットのペン習字通信講座は万年筆を使うことを前提にした通信講座です。
そのため、級位認定のための課題についても下記の通り説明があります
筆記具は、万年筆またはデスクペン
級位に関わらず、お気に入りの万年筆を使ってOKです!
パイロットペン習字の検定試験は、万年筆を学ぶ中級者以上にオススメ!
パイロットペン習字の検定試験にはお手本はなく、初心者が受けるには少し戸惑うかもしれません。
一方でパイロットペン習字はペン字の通信講座には珍しく、万年筆を使うことを前提としています。
そのためボールペンや鉛筆ではなく万年筆を学びたい人は、講座を受けつつ検定試験を受けることで万年筆の実力がついていくのを実感できます。
まとめ:自分に合う資格を見つけ、昇級を目指し実力を高めていこう


本記事のまとめです!
・最もオフィシャルな資格は、日本書写技能検定協会の硬筆書写技能検定
・万年筆使用可能なのは日ペンの師範認定試験、全国ペン硬筆検定試験、パイロットペン習字の検定試験の3つ
ペン字についての資格は数多くあり、その特徴も様々です。
資格取得も大事ですが、そこに至るまでにしっかりと学習を積み重ねることも重要です。まだペン字学習をはじめていないよー、という方には是非ともペン字学習をはじめてみませんか?大人になってからも始められる新しい趣味にとてもおススメです!



僕も少し前まで「字なんか書いて何が楽しいの?」と思ってたけど、今は毎日寝る前の練習の時間が楽しいよ!


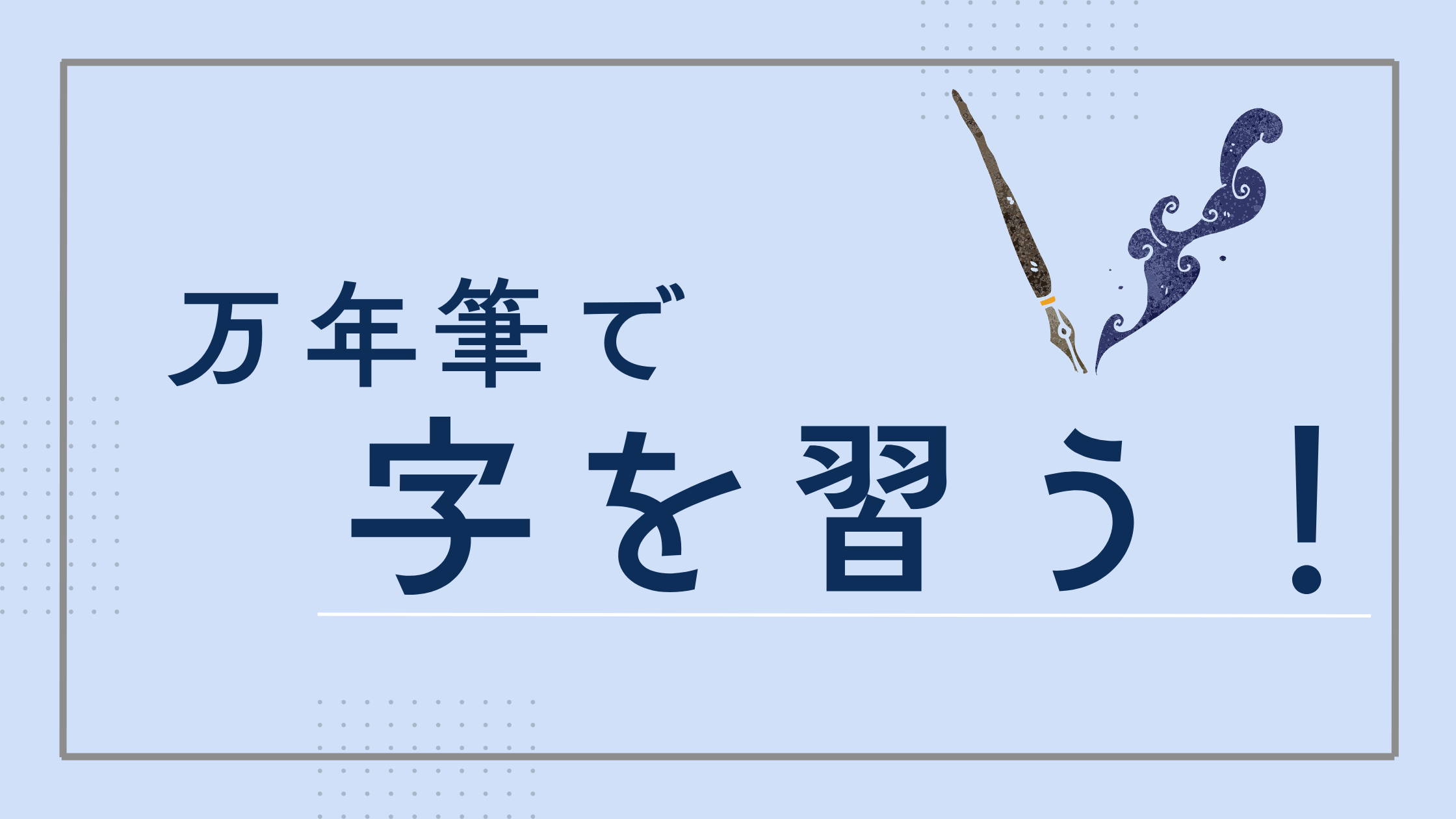
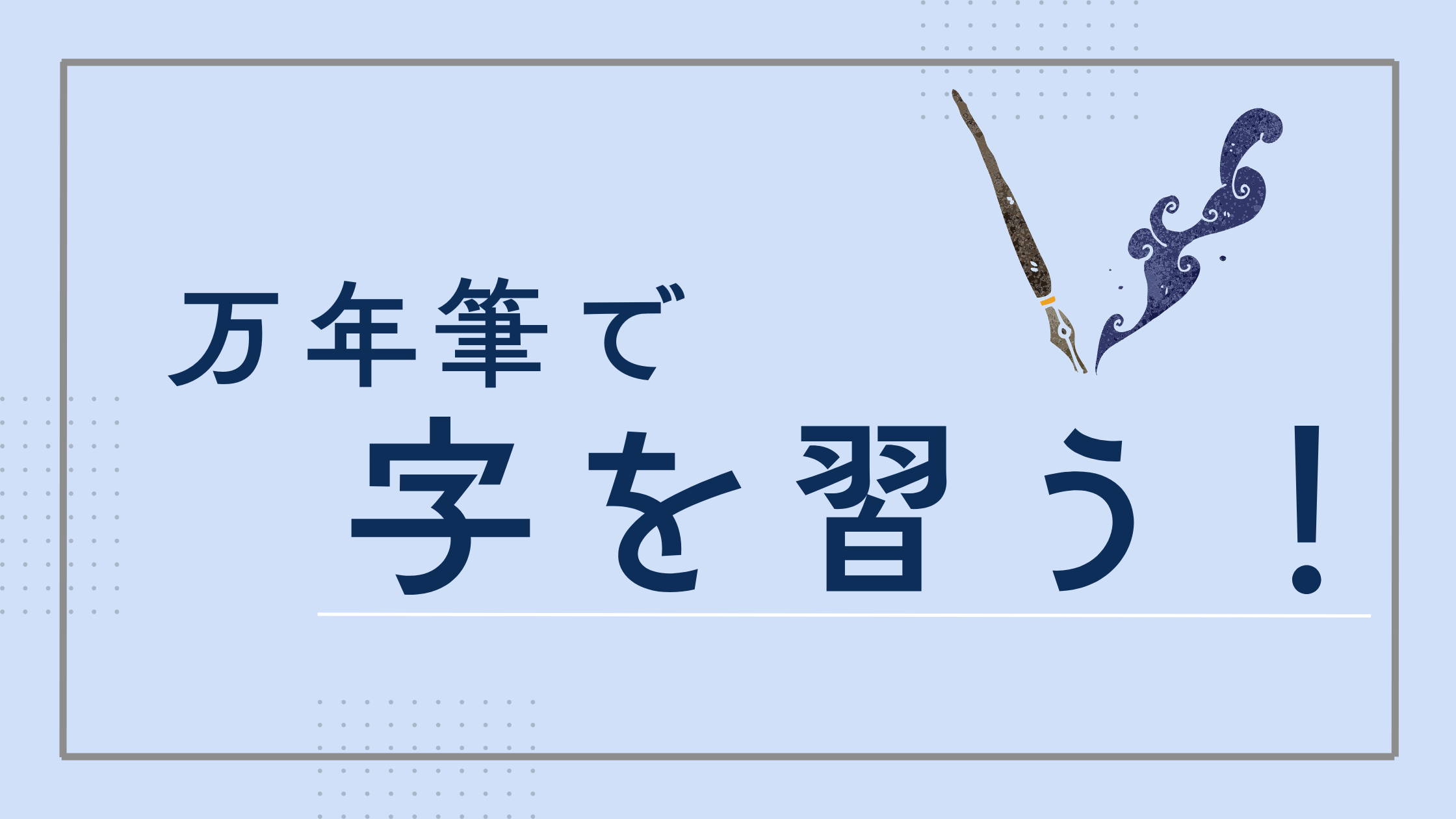










コメント